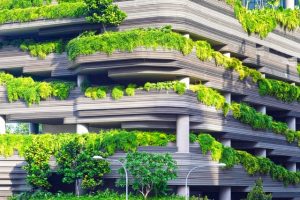BIMやCIMというワードをご存知でしょうか。
これらの技術は分野の枠を超えて、近年様々な場面で耳にすることが多くなってきました。
建設業界では、業務連携やプロジェクトコストの合理化など、様々な活用が見込まれています。
しかし、まだまだその認知は低く、そもそもBIMやCIMが何を指す言葉なのかわからないという方もいることでしょう、今回は、そんなBIM CIMについて様々な事例と合わせてご説明していきます。
BIM/CIMとは?それぞれの違いを解説
BIMとは「Building information Modeling」を略したものです。
コンピューター上に建築物の3Dモデルを制作し、設計から施工まで業務に関わる様々な情報を連動させる手法です。
BIMではモデルデータを相互に共有できるので、様々な情報を一元化して取り扱うことができ、主に建築分野で利用されています。
一方でCIMとは「Construction Information Modeling/Management」を略したものです。
こちらも、コンピューター上に構造物の3Dモデルを制作し、設計から施工まで業務に関わる様々な情報を連動させる手法です。
CIMは業務の効率化だけでなく、現場状況の分析などでデータを収集・反映を目的としており、主に土木分野で利用されています。
それぞれ詳しく解説していきます。
BIMとは?
BIMの一番の特徴は『情報の一元化』です。
企画から設計、施工に維持管理まで様々な工程に分かれ複雑な建築業務ですが、3Dモデルを活用することであらゆる情報がリンクされ、BIMを使ったリアルタイムでの情報共有が行えるようになりました。
建物の形態だけでなく、建具の品番やメーカー、価格といった情報も含まれており、スケールに制限されることなく情報が集約されています。
そのため、コミュニケーションがスムーズになっただけでなく、これまで段階的に進められていた事業工程が並行して行えるようになり、大幅な工期短縮にも繋がりました。
また、近年は業界にかかわらず資源の有限性が大きな課題となっています。
BIM導入により、建設材料の無駄が減ったり、モデルを利用した様々な分析を通じて環境負荷を抑えたりすることができ、コストカット以外にも様々な利点も注目されています。
もうひとつ、プロジェクトの全体像を予め用意することができることも大きな特徴でしょう。
BIM上では、それぞれの工程が3Dモデルとして反映されるため、イメージの共有が容易となり、専門知識がない方とも協働して計画を進められるようになりました。
まとめると、BIMとは模型のような3Dモデルをコンピューター上に作成・共有することで計画のアクセシビリティが飛躍的に高められる技術といえるでしょう。
CIMとは?
CIMも機能はBIMと似ていますが、用途が少し違います。
CIMとは土木業務で重要なのは完成後の維持管理工程が、計画から完成までのプロセスと同等、それ以上に大切なものになっています。
ダムなどの発電施設ではランニングコストやメンテナンスの頻度、橋やトンネルといった交通インフラでは工事の際に生じる交通渋滞などが懸念されます。
こうした問題を整理するためにも、膨大な情報を反映し、分析するためにCIMの導入が増えてきています。
地形の立体データをつくることはこれまできわめて難しいものでしたが、最近はドローンによる空からの撮影や、コンピューターの解析能力が向上してきたことから、CIMを用いた複雑な地形の再現ができるようになりました。
CIMによる3Dデータが現場の作業員の安全のために導入されるというケースも多くあります。
土木分野では全行程を通して、膨大な人員が入れ替わりながら関わります。
一方、現場状況は複雑で状況に応じて作業内容がすぐに変わってしまうことが頻発します。
こうした状況下でも、安全に業務が行えるよう、CIM技術を生かした教育プログラムが作成されています。
まとめると、CIMとは3Dモデルをコンピューター上に作成・共有することで、複雑な計画の全体像をだれもが簡単に把握できるようにする技術といえるでしょう。
BIM/CIMそれぞれの事例を紹介
では、実際BIM/CIMそれぞれの事例をみていきましょう。
BIMの事例とできること
事例:上海タワー(上海・2016年)
BIMの活用目的:コストの低減、 チャレンジングな構造の実現、 多国籍の同時連携
BIMを利用した有名な事例の一つに、中国の上海タワーがあります。
世界第2位の高さを誇るこの建築物は、当時様々な課題を乗り越えて建造されました。
一番大きな課題は、技術面での情報連携です。
建設当初から構造面において挑戦的な方法が見込まれていたため、BIMを用いて進めることにしました。当時採用されたのはRevitというBIMソフトウェアで、多言語対応のものが導入されました。
結果、様々な国をまたいで優秀な技術者とのリアルタイムでの連携が可能となり、国内最大の建造物として実現することになります。
工期短縮や合理的な工事方法の提案も同時に行われ、施工のマネジメントに関しても大きく貢献しました。
驚くべきことに、BIMシステム採用の副産物として従来のタワー建設よりも32%も資材を削減できていたそうです。
構造的にも、環境的にも快挙を成し遂げた上海タワー。
その建設の裏には、場所に関わらないグローバルなプロジェクト進行を可能にしたBIM技術の存在が大きかったようです。
Bimの活用事例について詳しくはBIMの活用事例と導入の問題点を徹底解説の記事で紹介しているので合わせてご覧ください。
CIMの事例とできること
事例:渋谷駅周辺開発(東京・2018)
CIMの活用目的:マネージメントの高度化、イメージの共有、リスクの低減
CIMを利用した有名な事例の一つに、近年行われた渋谷駅の周辺開発事業があります。
事業者、建築家など様々な主体が協働で進める国家的プロジェクトでした。
渋谷の再開発事業の中でも難所だったのが、銀座線渋谷駅の移設工事です。周辺の事業との綿密な調整が必要なため、変化が即時に反映されるCIMが導入され、情報共有の有用性が発揮されました。
CIMの利用は設計施工業務の効率化だけでなく、計画によって発生する費用的損害を抑えることにも繋がります。
移設工事の際には、何度も線路切り替えを行うこととなります。
それぞれに生じる電車や人の動線パターンを分析する際にもCIMデータが利用されました。
人通りが減ったり、工事のために通行止めの箇所が増えると、店舗の営業に大きな支障を生じます。その点を考慮した施工方法が検討されました。
また、現場では多くの人材や事業者が協働することになります。
混乱を避けるためにも、CIMデータを分析することで施工リスクが予見され、すぐに指導プログラムに反映されます。このように、各作業員の動きの合理化や安全確保が実現されました。
BIM/CIMとは?それぞれの違いと事例解説のまとめ
ここまで見てきたように、BIMの特徴は情報を共有することで、短い建設期間の中で複雑建築物の実現を可能にすることです。
上海の事例以外にも、国内外で挑戦的な意匠の建築物がふえてきています。今後ますます利用されてくるでしょう。
また、CIMの特徴とは安全でスムーズな施工計画を立てるため、現場の情報を集め・反映することです。
複雑な対象を精緻に分析し、新しい姿に変えるという工程は、都市のみならず災害の多い日本の様々な場所で見られます。
建築や土木に関わらず、技術の発達とともに膨大な情報を集めることができるようになってきています。
そうした情報をうまく利用するためにも、BIMやCIMなどの技術が今後ますます利用されることになるでしょう。